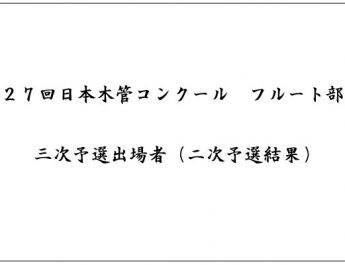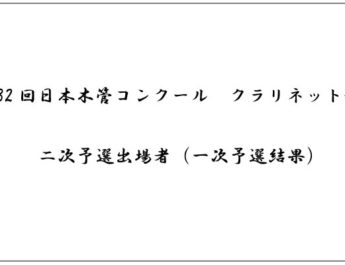山本 正治
東京藝術大学名誉教授、武蔵野音楽大学特任教授 〈審査委員長〉
1次予選終わり14人の方が残りました。演奏には楽器を演奏する技術力と音楽を作る音楽的センスが要ると思います。技術力を身につける為にはロングトーン、音階などの基礎練習。
基礎練習をする為にも音楽的センスが無いとただ楽器をコントロールするだけのテクニックが身についてしまいます。音階練習する時も頭に作曲家が浮かんでいると良いです。
センスを身につける為には、オペラ、弦楽器、ピアノの演奏会などに行って、まず自分が沢山感動すると良いです。今回の1次の課題曲は、Stravinsky、Donizetti、またKovácsのHommage à M.de.Falla ・ Hommage à R.Strauss とそれぞれに作曲家の個性が強い曲です。
R.Straussはオペラ「薔薇の騎士」、M.de.Fallaは「三角帽子」など譜面見ながら勉強すると良いと思います。Fallaの曲はスペイン風のリズムが大事ですし、Hommage à R.Straussの最初のリズム、途中のLangsamの歌う感じ、また3拍子のワルツの感じなどはオペラ「薔薇の騎士」に似てるところが沢山出てきます。良い演奏家になる為に沢山管楽器以外の演奏会に行ってください。
磯部 周平
昭和音楽大学客員教授、東邦音楽大学特任教授 〈運営委員長〉
先ずは自分を認めたい。
他人はそれを『過信』と言うかも知れないけれど、充分自分を信じて、少なくとも将来、夢見た自分に近づく事を信じたい。その上で、作品の背景、時代の空気、一曲の作品を創造するずば抜けた作曲家達の心と楽譜を今出来るあらゆる手段を使って研究したい。
ドニゼッティはいつの時代の作曲家か‥今回残念ながら自分の方へ作品を引き寄せ過ぎた人が多数。
ストラヴィンスキー がわざわざ八分音符は16分音符3つの長さと楽譜に書いているにも関わらず、曖昧な演奏がありました。(『春の祭典』には16分の5拍子が沢山!)
コヴァーチさんの作品は「オマージュ」なので作曲家への愛、尊敬や畏敬を素通りして音符だけを追っては片手落ちです。
自分への愛は大切に育てつつ、作品が教えてくれる今の自分に足りない部分をしっかりと把握しましょう。
他人と比べる、競うというコンクールだからこそ、自分を信じ、じっくり作品と向かい合う幸せと音楽が出来る喜びを感じてほしい‥と思いました。
小谷口 直子
京都市交響楽団 首席クラリネット奏者
何度でも録り直しをできる動画提出よりも、舞台の上でこの日この時に一発本番、のほうがずっと難しいはずですが、皆さん総じて予備審査の時よりずっと完成度高く仕上げてこられていたことがとても印象的でした。二次・本選の曲の準備も、コンクール以外の日々の活動もある中で、自分で選んだとはいえ、一次の「この1曲」から逃れられない数ヶ月を過ごすのは本当にタフなことだったと想像しますが、向き合う時間が、作品が、生の舞台が、目を見張るような成長をそれぞれに授けてくれること、改めて素晴らしいと感じました。個人的には、速くて凄い演奏(←羨ましいですが)よりも、全ての音に耳と心が届いているのがはっきりと聴こえる演奏が好きです。残念ながら二次に進めなかった人の中にも、そのような演奏はいくつもあり、嬉しかったです。皆さんそれぞれの明日へ向けて、また元気に頑張ってください◎
十亀 正司
武蔵野音楽大学非常勤講師、(株)亀の子音楽工房代表取締役
クラリネットコンクールの一次審査を終えて感じたのは、年々全体のレベルが確実に底上げされているということです。その中で最難関ともいえる一次を通過するのは容易ではなく、通過できなかった人の中には実力だけでなく運や当日の体調といった要素も影響したかもしれません。このコンクールの課題曲はいずれもテクニカルな側面が強く、皆さん高い技術で演奏していました。しかし、次の段階へ進むためには、音符を正確に並べるだけでなく、それをどれだけ音楽的・メロディックに表現できるかが鍵になります。フレーズを意識し、単なる音の羅列ではなく「歌」として聴かせる感覚が求められます。全体の水準が上がった今、技術だけでは差がつかず、音楽としての説得力こそが評価を分ける時代になっていると強く感じました。
中舘 壮志
読売日本交響楽団首席クラリネット奏者
1次予選が1番難しいのだなと強く感じました。あの緊張感の中、与えられた時間は5分弱で、その間に色々なことをアピールしなければなりません。人よりテンポを速くするのも1つの作戦かもしれませんが、技術的な平均レベルが高くなっている為、それが通用しなくなっている様に感じます。
ドニゼッティ、コバーチは音階、アルペジオを雑に吹かず、和声をもっと大切にしてほしい。ストラヴィンスキーは1曲目のアーティキュレーションが聴き取れない人が多かったのが気になりました。
それぞれの作曲家の他の作品(オペラ、交響詩など)のフレーズを思い浮かべながら演奏すると、速くヴィルトーゾに吹く事よりも大事なことが見つかると思います。
ブルックス 信雄 トーン
愛知県立芸術大学 准教授
日本木管コンクールの審査を務めることは、いつも私にとって大きな光栄です。今年も若い演奏者のみなさんの演奏を聴き、多くの刺激を受けました。
日本の若い演奏者のレベルは毎年上がっており、多くの方がとても高い技術を持ち、ほとんど間違いなく演奏していました。そのため、今回の予選で人数を絞ることは本当に難しい作業でした。
私が最後の判断で大切にしているのは「表現力」です。技術はもちろん重要ですが、それだけでは音楽の魅力は十分に伝わりません。曲の感じ方やフレーズの流れ、音にどんな思いを込めるか――そういった部分にも、これからぜひ同じくらい力を入れてほしいと思います。
聴く人の心に残るのは、やはり演奏の「表情」や「気持ち」です。みなさんの今後の成長を楽しみにしています。
三界 秀実
東京藝術大学教授
今回の審査はいつにも増してレベルが拮抗しており、本当に難しい審査となりました。
何十人もの人が当落線上にいたような印象です。
これまでのコンクールであれば「もっと楽譜通りに」とか「作曲家の持つ様式感を考えて」といった言葉がすぐに浮かんできたものですが、今回はそんなレベルを軽々と超えている人たちが半数以上はいたのではないでしょうか?
残念ながら結果が伴わなかった人はあまり悲観せず、今回はたまたまの結果だと割り切って次の目標に頭を切り替えて欲しいです。
コンクールというものは音楽の広大な世界の中ではほんの一部分にすぎない、ということも忘れずに。
ただできれば2次、本選の演奏を聞いてください。
多くの他の人の演奏を聞くことで、自分の演奏を客観的に見つめ直すきっかけになるかもしれません。
そしてその中から必ず新しいヒントを見つけることができると思います。